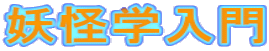
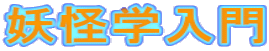
| 人は、恐ろしい体験をすると、『怖い』と感じると、思いがちですが、実は違うのだそうです。人は、突然、恐ろしい体験をすると、まずは、『驚く』のだそうです。 『怖い』という感情は、経験や知識の裏づけが有って初めて生じる感情なので、あらかじめ予測していないと恐怖心は起こらない。例えば、お化け屋敷に入る場合など、入れば、恐ろしい物に遭遇すると、解っているから、『怖い』と感じることができるのです。 さて、突然、未知の体験をした(深夜に川岸を歩いていたら、不気味な音を聴いた)場合は、アドレナリンが大量に分泌され、副腎皮質ホルモンも分泌されます。そのことにより、顔は青ざめ、心臓がドキドキし、緊張して筋肉の力が抜けます。いわゆる、腰が抜けたりするのです。この現象は、起こっている事実によって引き起こされているのではなく、自分自身の『驚愕』によって、勝手に引き起こされている、医学的現象なのです。同じ意味で、いわゆる『きつねやたぬきにだまされた』も、自分で勝手に『だまされたつもりになっている』のですから、充分に科学的に説明ができる現象なのです。 さて、一時的ではあっても、このような状態(驚愕ヒステリー・驚愕神経症)になった人は、その後、落ち着いて、症状が治まってから、考え始めるのです。「あれは、なんだったのだろうか」。 人は、よほど、科学技術的にも人文学的にも、知識を蓄えている人ならば別ですが、一般の庶民は、それほど多くの知識は持ち合わせていません。特に、民話や伝承が盛んに形成された江戸末期から明治時代の庶民は、なおさらです。しかも、人は、そのときの自分が、正常な精神状況では無かったとは、認めたくないものです。そこで、まるで言い訳をするように、それが、例えば、河童や妖怪の仕業だったのだと、自己正当化する。これが、精神医学的な側面からの、民話発生プロセスなのです。 |
